
キプロス共和国で2015年12月10日(木曜日)に第8回 IEEE/ACM International Conference on Utility and Cloud Computing (
UCC15)において「FELIXの日」が開催されます。
第2回 International Workshop on Trust in Cloud Computing の中で、11時から Umar Toseef(EAST、ドイツ)が「
Authentication and Authorization in FELIX」を発表します。
ポスターとデモ・セッションの中で、下記の2つのプレゼンテーションを表示します
- Atsuko Takefusa (AIST, Japan) が「Business Continuity Planning with FELIX」を発表
- Łukasz Ogrodowczyk (PSNC, Poland) が「High quality media streaming over long-distance network using FELIX experimental facility」に関してデモ発表
コンファレンスのプログラムは
ここにあります。...
Read More »
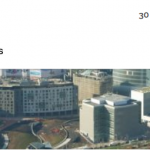
ビルバオの
EWSDN2015 Conference の中で、FELIXプロジェクトのチュートリアルが2015年9月30日に開催されます。
以下英文でFELIXのチュートリアルの概要を示します。
FELIX tutorial abstract:
Software Defined Networking (SDN) has altered the network R&D mentality with respect to the time required from concept validation studies to market introduction. In this context, innovative ideas need a test environment as close as possible to real-world scenarios. This has triggered international cooperation...Read More »

Gino CarrozzoとKostas Pentikousisは、2015年7月22日にプラハ、チェコ共和国で開催されたIETF 93 SDNRG MeetingのIRTF SDNRGで「Framework for Large-scale SDN Experiments via Software Defined Federated Infrastructures」を発表しました。発表内容は
ここからダウンロードできます。
...
Read More »

マレーシアのクアラルンプールで開催された
第40回APAN Meetingの中で、
KDDIの田中 仁は8月14日の「
Network Engineering Workshop」で「
Large-scale SDN experiments in federated environments」を発表します...
Read More »

Umar Toseefは
OGF 43 meeting in Washington DCで「FELIX and NSI: Mutual Authentication and Authorization」を発表しました。
Open Grid Forum (OGF)は、クラウド、グリッドと関連するストレージ、ネットワーキングおよびワークフロー方法を含め、現代の高度な適用される分散コンピューティングに対して急速な進化と採用を推進することをコミットしたオープングローバルなコミュニティです。 第43回OGF会議では、NSIによるトランジットネットワークとFELIXテストベッドの間にオンデマンドで接続を確立するための認証および承認を得るメカニズムを提案したした。...
Read More »

FELIXのチュートリアルは、MONAMI 2014 会議の中で「SDN Experimentation Facilities and Tools」のトピックの下で発表されました。
チュートリアルの最初の部分は、ヨーロッパと世界規模の利用可能なSDN実験施設に関してです。特にSDN技術がOFELIAとGENI実験施設の基盤を形成する方法を具体的に議論しました。そのような実験施設において多種多様なネットワークデバイスの追加が可能かを示しました。
具体的には、技術革新に焦点を当てたチュートリアルでは、FP7のALIENやFELIXプロジェクトによってもたらされた技術革新に焦点を当てました。これらは次の能力を拡大します。
a) 新しいSDN実験施設を作るために利用可能なオープンソースのソフトウェア
b) 現在のデプロイメント動向
c) 利用可能なソフトウェアを強化し、ヨーロッパと世界中の実験施設の設置面積を拡大する機会...
Read More »
2014年3月19日に FIA 2014 confernceのCloud Federations and SDN session にて、Bartosz Belter (PSNC) がSDN対応のクラウド連携に関するエネルギー効率を達成するためのFELIXのユーズケースを紹介します。
ここで発表のライブを見ることができ、
発表資料を通して彼の主要な考えを理解できると思います...
Read More »
アテネの
FIA 2014 カンファレンスの
Network Virtualization Workshop で、Kostas Pentikousis (EICT) は FELIX プロジェクトについて講演します。2014年3月18日に
ここで発表のライブを見ることができ、
発表資料を通して彼の主要な考えを理解できると思います。...
Read More »
2014年3月12、13日にベルギーのブリュッセルにおいて、「oncertation Meeting - E2 Software & Services, Cloud Computing | Towards an interoperable European Ecosystem of services」が開催されます。この会議の目的は、以下の議題を通してプロジェクト間の連携·交流を促進することです。
- Unit E2 (calls 5, 8 & 10, CIP and EU-Japan) のすべてのプロジェクトの活動についての勉強会
- 他のコンソーシアムやパートナーの発掘と交流
- 各自のアイデアの発表と意見交換
- FP7からH2020への変更の理解と、それに起因する新たな機会を探る
FELIXは、「Internet of Services & heterogeneous clouds」セッションのライトニングトークに招待されています。
ウェルカムレターと会議の
詳細情報です。...
Read More »
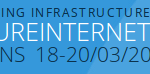 Workshop Details:
Workshop Details: 17 March 14:00-17:30 and Tuesday 18 March, 09:30-13:00
Workshop online agenda: Day 1 Day 2
FIA2014 Programme, including Pre-FIA Workshops: http://www.fi-athens.eu
Exhibition: http://www.fi-athens.eu/exhibitors
欧州委員会のFIREプログラムは、将来のインターネットのアプリケーション、サービスおよび技術に取り組むための、大規模なテストベッドおよびプラットフォームをヨーロッパに構築しています。FIREの設備は将来のインターネットの開発の重要なメカニズムとなる実験主導の研究や革新を支援してきました。多くのFIREの設備は公開され、広く利用されています。今後、ECや国家の資金が終了した後でも、これらの設備の持続を可能にする方法を模索しています。
FIREの発展: サステイナビリティーのための設備、サービスおよびコラボレーション・ストラテジー FIA2014 (
http://www.fi-athens.eu/)が2014年3月17、18日にアテネにおいて、AmpliFIRE、CI-FIREおよびFUSIONの主催で開催されました。FIREの設備を需要側と供給側の両方から見ることは、常に発展し続ける動的な生態系の作成による、持続性への道を決める助けとなります。ビジネス・プレーヤーの要求と将来のインターネットの設備に関連したFIREの役割を考えて、ワークショップはビジネス、サービス関連、インフラストラクチャー、FIRE内外の技術的・組織的な共同作業などの機会に注目しました。
供給側から見ると、本ワークショップはFIREプロジェクト、開発者とオペレーター、FI-PPP、EIT ICTラボ。Livingラボなど国や地方のテストベッドと同様なテストベットの提供側をターゲットにしています。提供側からみると、本ワークショップは、種々の分野に跨った新しい製品やサービスの有効性を通して、事業の創造や革新を促進するための洞察力を獲得しようとする中小のビジネスや大企業をターゲットにしています。...
Read More »
2014年2月21、22日に FELIX パートナーは、FELIX フレームワークの実装の詳細を議論するために、バルセロナで集まりました。特定の機能ブロックの通信インタフェースとフレームワークのワークフローを徹底的に議論しました。これにより、テストベッド環境でユースケースを実行することができるようになり、最終的な FELIX の展開を決定できました。特定のツール、技術および規格を適切に選択し、2014年の第4四半期でのプロトタイプの動作していることを期待した FELIX 実装のロードマップを定義しました。...
Read More »

Asia Pacific Advanced Network (APAN, www.apan.net) は、研究、教育、社会に利益をサポートするための国立研究教育ネットワーク(NREN)の開発と利用に関する会議を毎年2回開催しています。この第37回目の会議(APAN37)が2014年1月20日から24日の間、インドネシアのバンドンで開催されました。 FELIX-EUのコーディネーターは、「今後のインターネットテストベッド」セッションで、ヨーロッパと日本の相互協力の最初の経験について講演をするために招待されました。
詳細な情報は
http://www.apan.net/meetings/Bandung2014/index.php を参照してください。...
Read More »
2013年11月18から21日にかけて SC13 (http://sc13.supercomputing.org) がコロラド州のデンバーで開催されました。SC13は、業界や研究機関が開発した製品、ソリューション、研究対象を世界中に実証する絶好の機会でした。 FELIXの新しい概念を研究コミュニティに紹介するため、FELIXプロジェクトはSC13に参加しました。...
Read More »
2013年10月24、25日にFELIXの全体的なアーキテクチャを定義するため、主なパートナーがフランクフルトに集まりました。この結果、
D2.1 Experiment Use Cases and Requirementsが完成しました。D2.1は、FELIXのユースケースへの展開とその要件で構成されています。一般的なアーキテクチャと主要な機能ブロックの定義が本会議のアウトプットです。これらにはFELIXの基本的な機能性の状態とワークフロー含まれます。アーキテクチャは、実装技術の選択を制限しないように、各種技術や様々なツールの選択や再利用およびインタフェース定義には一般的な方法で定義されています。この結果としてFELIX全体的なアーキテクチャは公開されました。...
Read More »
2013年9月12日、13日、プロジェクトの成果を実践したのユースケースに関して議論するために、FELIXパートナーはベルリンに集合しました。各ユースケースは、パートナーが様々な目的のために研究、実装したいと思っている実ケースであり、例えば、性能試験、実際の問題解決や概念の検証などです。6ユースケースについて議論されました。これらのユースケースに基づいて、アーキテクチャ定義に必要なユーザの要件を定義しました。...
Read More »
2013年7月2日に東京において、総務部 (MIC) と情報通信研究機構 (NICT)と共に欧州委員会は FELIXを含む 6 研究プロジェクトの立ち上げを発表しました。東京のイベントでは、欧州委員会、総務部と情報通信研究機構は日欧協力となる ICT 研究プロジェクトの開始する覚書に調印しました。プロジェクトの共通した目的は、データネットワークを進化させることです。
このイベントは、広くマスコミでコメントされてます。詳細は
ここを読んでください。...
Read More »
最初のプロジェクト会議は2013年6月7、8日にオランダのマーストリヒトで開催されました。会議の目的は、すべてのパートナーの顔合わせを行い、プロジェクトを開始することでした。...
Read More »
2013年6月3日から6日に、オランダのマーストリヒトでTERENAネットワーキングコンファレンス(TNC2013)が開催されました。ヨーロッパの研究ネットワークの最も有名な会議として、多くの科学コミュニティー、技術者や企業から注目を集め、5400人以上が出席者しました。
FELIXはプロジェクトのコンセプトと目的を論文をTNC2013で発表しました。この論文では、SDNクラウド(データセンタ)上のある各種資源を、OpenFlowなどによって制御されたネットワーク・サービスによって、エンド・ツウ・エンドで接続する新しいフレームワークについて報告しました。また、データセンタ間の相互接続性を実現するSDNやNSI-CS、資源をスライスとして動的に管理するメカニズムなどを統合しました、新しいNSIサービスを提案しています。本フレームワークは既存のNSIモデルを拡張し、多地点のSDNで制御されたネットワーク間を接続するサービスを可能にしました。その結果、複数の管理ドメインを跨いだエンド・ツウ・エンドの接続サービスが提供できるようになりました。...
Read More »
 キプロス共和国で2015年12月10日(木曜日)に第8回 IEEE/ACM International Conference on Utility and Cloud Computing (UCC15)において「FELIXの日」が開催されます。
第2回 International Workshop on Trust in Cloud Computing の中で、11時から Umar Toseef(EAST、ドイツ)が「Authentication and Authorization in FELIX」を発表します。
ポスターとデモ・セッションの中で、下記の2つのプレゼンテーションを表示します
キプロス共和国で2015年12月10日(木曜日)に第8回 IEEE/ACM International Conference on Utility and Cloud Computing (UCC15)において「FELIXの日」が開催されます。
第2回 International Workshop on Trust in Cloud Computing の中で、11時から Umar Toseef(EAST、ドイツ)が「Authentication and Authorization in FELIX」を発表します。
ポスターとデモ・セッションの中で、下記の2つのプレゼンテーションを表示します
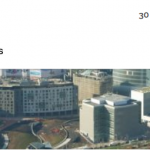 ビルバオの
ビルバオの 
 マレーシアのクアラルンプールで開催された
マレーシアのクアラルンプールで開催された Umar Toseefは
Umar Toseefは FELIXのチュートリアルは、MONAMI 2014 会議の中で「SDN Experimentation Facilities and Tools」のトピックの下で発表されました。
チュートリアルの最初の部分は、ヨーロッパと世界規模の利用可能なSDN実験施設に関してです。特にSDN技術がOFELIAとGENI実験施設の基盤を形成する方法を具体的に議論しました。そのような実験施設において多種多様なネットワークデバイスの追加が可能かを示しました。
具体的には、技術革新に焦点を当てたチュートリアルでは、FP7のALIENやFELIXプロジェクトによってもたらされた技術革新に焦点を当てました。これらは次の能力を拡大します。
a) 新しいSDN実験施設を作るために利用可能なオープンソースのソフトウェア
b) 現在のデプロイメント動向
c) 利用可能なソフトウェアを強化し、ヨーロッパと世界中の実験施設の設置面積を拡大する機会...
FELIXのチュートリアルは、MONAMI 2014 会議の中で「SDN Experimentation Facilities and Tools」のトピックの下で発表されました。
チュートリアルの最初の部分は、ヨーロッパと世界規模の利用可能なSDN実験施設に関してです。特にSDN技術がOFELIAとGENI実験施設の基盤を形成する方法を具体的に議論しました。そのような実験施設において多種多様なネットワークデバイスの追加が可能かを示しました。
具体的には、技術革新に焦点を当てたチュートリアルでは、FP7のALIENやFELIXプロジェクトによってもたらされた技術革新に焦点を当てました。これらは次の能力を拡大します。
a) 新しいSDN実験施設を作るために利用可能なオープンソースのソフトウェア
b) 現在のデプロイメント動向
c) 利用可能なソフトウェアを強化し、ヨーロッパと世界中の実験施設の設置面積を拡大する機会...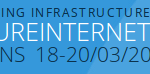 Workshop Details: 17 March 14:00-17:30 and Tuesday 18 March, 09:30-13:00
Workshop online agenda:
Workshop Details: 17 March 14:00-17:30 and Tuesday 18 March, 09:30-13:00
Workshop online agenda: 